🎥 作品情報
・公開年:1936年
・監督:チャールズ・チャップリン
・国:アメリカ
・ジャンル:喜劇・社会風刺・ロマンス
・鑑賞場所:U-NEXT
🌱 この映画を見た理由
「喜劇王って何がそんなにすごいんだ?」
そこから始まった。
モダン・タイムスは“今の時代にも刺さる”というのを何度も聞いていて、
仕事や生活に追われる自分が観たら、何かヒントになるかもしれないと思った。
鑑賞前から**“機械に支配される社会への風刺”**
というテーマだけは知っていたけれど、
実際に観てみたら想像以上に“今の自分の生活”と重なって驚いた。
そして…
「モダンタイムスって聞くとバラエティ番組しか浮かばない」
そんなミーハーな気持ちも少しあった。
🔍 見どころ1(印象的なシーン・テーマ)
ベルトコンベアに飲み込まれていく冒頭
笑えるのに、笑えない。
じわじわと胸が苦しくなる。
チャップリンが無限にネジを締め続け、
動きが“機械の一部”になっていく瞬間。
これを観たとき、**「あ、これ今の自分かも…」**と少しゾッとした。
社会人として働いていて、気づいたら
「プライベート」より「タスクの波」に押されて生活していることがある。
その感覚とピッタリ重なった。
給食機の暴走シーン
効率化の極み。
食事さえ「時短」の対象になってしまった世界。
笑いながらも、**“今の社会も、方向性としてはわりと同じじゃないか?”**と思ってしまう。
ワーカーの仕事をAIや自動化が奪うかもしれないと危機感を社会が認識し始めている2025年、
チャップリンの皮肉はまだ新鮮だった。
“人間の生活まで効率化の対象にしてしまう発想は、結局約100年変わっていない”と感じた。
🎭 見どころ2(キャラ・演技・音楽)
チャップリンの身体表現のキレ
言葉なしでここまで伝わるのか?というレベルの“動きの情報量”。
ストレス、焦り、希望、優しさ——
全部が身体で語られていく。
ガミン(少女)の存在
彼女が出てくるだけで映画の温度が上がる。
貧しさと無邪気さの間にある”生きる力”みたいなものが強い。
ラストの音楽
前向きなのに、少し切ない。
「それでも歩いていこう」というメッセージの背中を押される。
🧠 深掘り・考察
1930年代の大恐慌の影響
・大量生産・大量消費社会への移行期で、「人が機械に置き換えられる恐怖」が広がっていた。
・チャップリンはそれを喜劇として昇華し、人々に笑いながら希望を見せようとした。
現代社会とのリンク
・タスクに追われる働き方
・効率化の名のもとに心が擦り減る職場
・AI登場での「人はどこまで必要?」という不安
約100年前の不安が、今の俺たちとほぼ同じ。
自分の人生観につながった部分
・効率を求めすぎて“心の余白”を失っている
・どれだけ忙しくてもユーモアを忘れない生き方をしたい
・旅や本や映画で「人間らしさ」を取り戻す時間って大事
映画を観ながら、
「俺はすでに機械の歯車になってるのかも」と少し現実が怖くなった。
🎯 まとめ(感想と評価)
・時代を超えて刺さる“笑いと皮肉”が詰まった名作。
・ただの無声喜劇ではなく、人間らしさを取り戻すためのメッセージが込められている。
・見終わったあと「もう少し肩の力を抜いて生きていい」と思える作品。
(むしろ「肩の力を抜く努力」をする時代なのかもしれない。)
・自分はすでに歯車の一部として人間らしさを失いかけているのでは?と考えさせられた。
だけど何より——
“効率化の波に飲まれても、人間らしさだけは失わない”
そんなメッセージが心に残った。
一言で表すと?
“人間らしさを忘れないための約100年前からの警告とエール”
読者にオススメしたいか?
→ 映画好きはもちろん、忙しい社会人にもぜひ観てほしい。
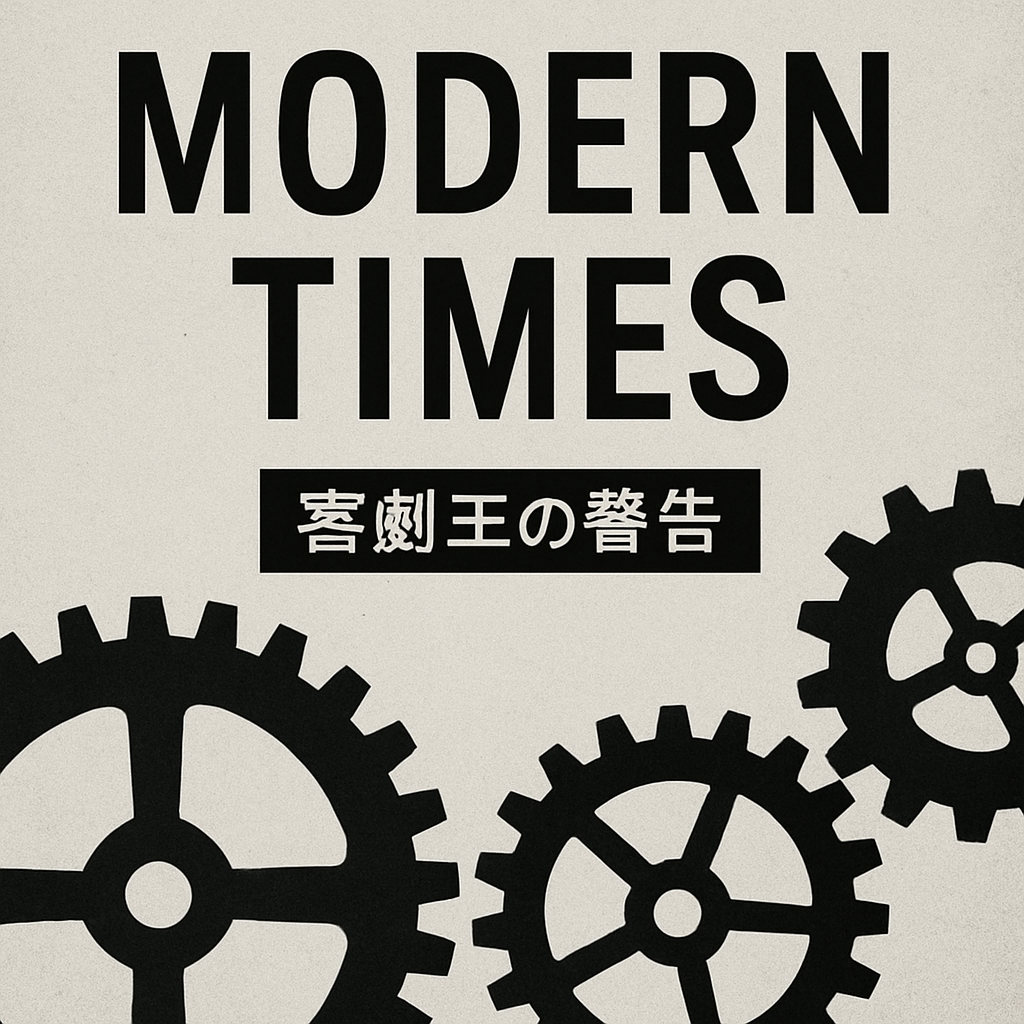

コメント